食中毒を予防しよう!
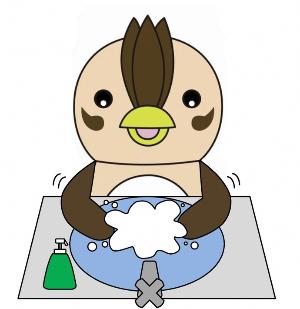
食中毒予防は、「菌をつけない」「増やさない」「消滅させる」が3原則です。そのうちの第1原則「菌をつけない」ためには「正しい手洗いの仕方」を取り入れて、手に付着している多数の病原菌を減らすことが大切です。
予防3原則を踏まえた、「食中毒を防ぐ6つのポイント」をおさえて食中毒を予防しましょう。
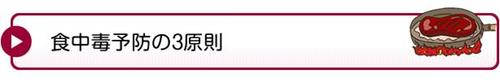



引用:食中毒予防の原則と6つのポイント | 暮らしに役立つ情報(政府広報オンラインのサイト)
食中毒を防ぐ6つのポイント
ポイント1 食材を買うとき
- 生鮮食品はなるべく新しいものを、食べきれる量だけ買う。
- 冷蔵や冷凍などが必要なものは、最後に購入し、寄り道しないで帰る。
ポイント2 食品を保存するとき
- 冷蔵、冷凍の必要なものは帰ったらすぐ冷蔵・冷凍庫へ入れる。
- 肉や魚は別々のビニール袋や容器に入れ、ほかの商品に触れないようにする。
- 食品は早めに使いきる。
ポイント3 下準備をするとき
- 丁寧に手を洗う。(特に生肉に触れたあと)
- 手洗いだけでなく、生肉を切った包丁やまな板はよく洗って熱湯をかける。(用途別にあるとより安全)
- 自然解凍は避ける。(解凍は冷蔵庫や電子レンジで)
ポイント4 調理をするとき
- 加熱して調理をする食品は十分に加熱する。(目安は中心部の温度が75℃で1分以上の加熱)
- 肉を焼くときは専用のトングを用意し、自分の箸で生肉に触れないようにする。
ポイント5 食事をするとき
- 食卓に着くときは手を洗う。
- 清潔な食器を使う。
- 出来上がったらすぐに食べる。
ポイント6 残った食品を扱うとき
- 清潔な手で、清潔な容器に入れる。
- 温め直すときも十分に加熱する。
- 時間が経ち過ぎたもの、少しでも怪しいと思ったものは食べずに思い切って捨てる。
正しい手洗いの仕方
手には見えない菌がいっぱい。手洗いは簡単で効果的な食中毒予防です。
- 指輪や時計などの装飾品を外す
- せっけんを十分泡立て、20秒以上もみ洗い
- 手首もよく洗う
- つめの間はブラシなどを使う
- 流水で30秒以上洗い流す
- 乾いた清潔なタオルでふく
ご注意ください!肉の生食・加熱不足による食中毒
調理者がどれほど努力しても、O-157(腸管出血性大腸菌)等の食中毒菌が肉へ付着する可能性があります。そのまま生で肉を食べると、食中毒になることがあり危険です。特に、体の抵抗力が弱い子どもや高齢者は、生肉を食べないよう注意してください。
O-157(腸管出血性大腸菌)とは?
0-157(腸管出血性大腸菌感染症)は、家畜や人の体内に存在する大腸菌で、ほとんどのものは無害ですが、いくつかのものは病原性大腸菌と言われ、下痢などの消化器症状や合併症を起こすものがあり、代表的なものは0-157があり、強い毒素により溶血性尿毒症症候群(HUS)などの重篤な合併症を引き起こすのが特徴です。流行時期は一般に気温が高くなる初夏から初秋にかけて多発します。0-157は、生肉以外にも井戸水、野菜類など、さまざな食品から見つかっていますが、他の食中毒菌と同様、加熱と消毒によって死滅させることができます。上記の「食中毒を防ぐ6つのポイント」を確実に実行し、食中毒を予防していきましょう。
もし食中毒になってしまったら
食中毒の主な症状は、嘔気・嘔吐、腹痛、下痢、発熱などです。同じ食事をした人に同様の症状があれば、食中毒の確率はさらに高くなります。十分な水分補給と、早めに医療機関を受診しましょう。
嘔吐(おうと)物等の処理には、手袋等を用いて2次感染に注意して取り扱いましょう。
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
健康推進部 地域保健課
〒358-0013 埼玉県入間市上藤沢730-1
電話番号:04-2966-5513
ファクス番号:04-2966-5514
メールフォームによるお問い合わせ


更新日:2025年01月16日